後期密教経典の和訳は多くないが、松長有慶が『秘密集会タントラ』については、全訳してくれている[1]。さらに、解説まで書いてくれている[2]。これをベースにして、その反社会性や性儀礼について見てみる。

『秘密集会タントラ』の歴史や生い立ちについては、無茶苦茶荒っぽく、前のブログに書いたので、その辺りは飛ばすが、興味あれば、松長の解説を見てね。
タントリズムの反社会性 ― 世俗論理の無視、戒律への反逆
まず、松長の引用から始めよう[松長、2006、P.46-p.47]
『秘密集会タントラ』の最も原初的な形を残している第五分[3]には、近代人の常識と真正面から対立する驚愕すべき記述が列挙されている。
このタントラによって成就を得る(悟るのに)に最もふさわしい者は、賤業に従事するアウトカースト[4]の人たち、無間地獄に堕すような大罪を犯した者たちであるという。それだけではない。殺人者、虚言者、盗人、愛欲に耽る者、沢尿を食する者こそが適格者だと宣言している。
(中略)
そのほか『秘密集会タントラ』には、五欲徳、五肉、五甘露など耳慣れ術語が現れる。
五欲徳とは、仏教が執着することを避ける色、声、香、味、触の五境を、逆に悟りへの手段として取り上げる。五肉とは、大・牛・犬・象・馬の肉で、そのうち大肉とは人肉と注釈されている。
五甘露とは、糞.尿・精液・経血・(油)などで、これらを食することが、成仏への道と指し示されている。る。このような常識をはるかに超える教説が、一般人の嫌悪感を誘い、顰蹙買う原因でもあった。
なんだ、これ!
ちょっと常識では、考えられない。
さらに、松長は続ける
しかし通常の社会から孤立し、人間より大宇宙を相手に自らの神秘体験の深化を求めるタントラの行者たちは、通常社会の倫理や規範に束縛される必然性はない。さらに仏教教団に属さない在野の行者たちもまた、もともと仏教の戒律に制約されるいわれをもたないのである。
現代に生きる普通の人間には、理解不可能だ!
この著書で、松長は、この反社会性について、「殺」と「淫」と「暗黒の呪法」の三点に絞って取り上げ、それらがタントリズムにおいて本来どのような意味をもつのかについて考えている。
続いてみてみよう!
性に対する寛容な姿勢[松長、2006、p.67]
『秘密集会タントラ』は、世尊が一切如来の身語心の心髄である金剛明妃の女陰において説くという、破天荒な宣言をもって始まる。
「女陰で説教する」
ひっくり返りそうだ!
まだまだ続く!
このタントラには、喩伽部の密教経典のように、修法にあたって印契(mudra)の記載がない。それに代わって大印(mahamudra)という語が現れ(第九分)、それは女性のパートナーを意味する。また男女の二根交会によって成仏にいたると説かれる(第七分)。さらに性交を、明妃の禁戒(vidyavrata)と名づけ、とくにナギー(龍女)、ヤクシー(夜叉女)、アスリー、マヌシーなどの異界の女性との交わりを薦めている(第一六分)。
(中略)
異様にみえる後期密教の性に対する開放的な姿勢も、性に対する放縦ではない。それは古代インドにおける農耕儀礼に由来する。
松長は、この異常な性に対する考えに対して、「インド人は、男女の性行為を古代の農民の豊穣儀礼から、宗教儀礼に転化させ、それに対してさらに哲学的な意味づけを行なった」と解釈した。簡単に言えば、「農耕民族→生殖→多産→繁栄」の図式だ。異常な性儀礼に対する非常に好意的な解釈だ。
それほど、インドにおける性意識は、異なるのだろうか?
ただ、性意識の異なる中国では受け入れられず、漢訳経典では、削除、異訳がなされているようだ。きっと日本でも、受け入れられないだろう!
さらに松長は「殺の肯定論」について、取り上げる[松長、2006、p.69]。
『秘密集会タントラ』における殺戮につては、3つの傾向があるそうだ。
1 殺生を主題として取り上げ、その意味についての神学的な解釈付与をする場合
2 殺人という行為に対して仏教的に意味づける場合
3 殺生を現実の行為として実行する生々しい呪法が記される場合
第七分の第三三偈に、「如来の聚を殺すべし。よい悉地が得られるであろう」とある。金剛界の五仏は五蘊を象徴する。従って如来の聚を殺すとは五蘊を自性として実態なしと破壊すべし、の意味だと、松長は解釈する。非常に仏教的な解釈だ!
密教において、殺害が許される場合とは、殺害によって多くの人が救われる場合、殺害によってその殺された人に出難の因縁ができるとき、いずれの場合にも大悲心がその根底にあるべきことを断る。この考えは『大日経疏』巻十七にあるらしい。
さらに「大悲の心、他人の利益を願う心があれば、殺生をはじめ盗、淫、妄語等ないという条件つきの殺害肯定論は、もともと大乗仏教の戒律に存在する」とも言う。
コメント===>なんだか、松長有慶の論は、敢えてこれまでの仏教の教えに寄り添う形のように思えてしまう。邪推すれば、密教徒である松長は、後期密教をできるだけ、宗門のこれまでの教理から外れたものにしたくなかったのかな〜〜
さらに松長は「暗黒の呪法の仏教化」について、解釈を進める。
『秘密集会タントラ』には、穏やかな治病法とか、解毒法とか、隠身法が説かれる一方、呪殺法、硬直法、恫喝法、粉砕法のように、恐ろしい呪法も少なくない。少し引用しよう。[松長、2006、P.72]
尸林(墓場)や斎場の灰や墨や骨粉などによって、敵対者の像を作り、毒草、棘、毒芥子などを用い、糞尿で汚れた着物を着け、怒りの心をもって修法に当たれば、敵対者はたちまちのうちに死にいたる、というようなおどろおどろしい呪法に関する記述が、いたるところに充満している(第一三分 〜 第一五分)。
(中略)
『秘密集会タントラ』の後半部には、このようなもともと仏教には存在しない各種の呪法が数多く摂取され、体系化されずに無造作に並べたてられている。それらは在野の行者集団の中で執行されていたいかがわしい呪法が、そのまま仏教側に採用されたものとみてよいであろう。
コメント===>松長は、恐ろしい呪法が初期密教経典にも現れることを述べてはいるが、基本的には、「怨敵の降伏法を阿閦如来の三摩地とみなし、密教化しようとする。また、敵対者の殺害を、痴の破壊と意味づけ、あるいは殺生という行為を、殺害された者を文殊の仏国土に送り、仏教徒として再生させるためだと仏教的な会通と行う」と述べ、呪祖を仏教的な意味付けの中に見出そうとしているように見える。
コメント===>ちょっと、仏教に肩入れしすぎのような気がするが、松長の立場としては、こうなるのかな〜。
自分の宗門(および、その発展)があまりにも反社会的だと、やっぱり生きづらい。
自分の宗門はやはり聖なるものであって欲しい気がするのだろう。分かる気がする。
ただ、それだけでは、後期密教は片付けれないような気がするがな〜〜。
個人的な妄想だろうか?
別に「偉大なる松長有慶先生」に楯突くわけではないが、もう少し掘り下げる必要があるような気がする。
後期密教の性的、反社会的な儀礼に対して、今後深掘りしていこう。
[1] 松長有慶、『秘密集会タントラ和訳』、法蔵館、2014
[2] 松長有慶、「秘密集会タントラー欲を生かして育てる」、松長有慶編『インド後期密教』(上)、春秋社、2006、p.37-82
[3] 18の分(章)から成る。チベット語訳では、第一分から十七分までを「根本タントラ」、十八分を「続タントラ」として区別する。なお、第十八分では、(第一分と第十八分を除く)諸分の分類は、五、九、十三、十七 :諸仏・諸菩薩の説く大成就、四、八、十二、十六:阿闍梨の事作法である、悉地の禁戒・律儀、二、六、十、十四:荒行・随貪としての近成就の律儀、三、七、十一、十五:悉地の場所・瑞相としての前成就の律儀と説明される。(https://ja.wikipedia.org/wiki/秘密集会タントラ)
[4] 不可触民(untouchable)とは、インドヒンズー社会にはカースト制度と言う身分制度があるが、その外側にあって、被差別民であり、アウトカーストと呼ばれる。



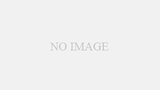
コメント