仏教といえば、「静かに座って瞑想する」「慈悲の心で生きる」というイメージを持ってしまう。ところが、インド仏教の最後に現れた「後期密教」は、そのイメージを大きく裏切るのだ。男女尊格が交合する像、墓場での修行、人骨を飾った装身具、そして性的な儀式……。
中期密教では、「仏そのものになる」ことを目指し、そのため、真言、手印、曼荼羅などの儀礼により、宇宙の本質と一体化し、「一気に悟る」ことを目指してたのだが、、、。それが、どうして後期密教に変容したのだ!
なぜ後期密教になるとここまで激しくなったのか、色々なことが言われる。後期密教化(もしくはタントラ化)と言われる動きは、仏教に限らずヒンズー教などでも起こった汎インド的動きであったようだ[1]。当時のインド社会に広まっていた女神信仰(シャークティ信仰[2])やシヴァ神を中心とするヒンドゥー教タントラの影響が言われるが、仏教もその流れに乗ったのか!
男女尊格が交合する父母仏については、これは単なる性的表現ではなく、「智慧(男性)」と「慈悲(女性)」の合一、つまり悟りの象徴だと言われる。
む〜〜〜、でもあえて、男女が抱き合っているという性的な表現でなくてもいいような気もする。
恐ろしい血の入った髑髏の杯を持つ女神「ダーキニー」は、修行者を悟りへと突き落とすと言われることもある。
でも、敢えてこんなに恐ろしげなものでなくても、、、と思ってしまう。

修行の場が墓場や屍林である必要があったのか?死を目の前にした極限の状況こそ、「生死を超える智慧」が得られるという。
いえいえ、他にもあるだろう!
「堕落」
「エログロ」
「そんなもの、仏教じゃない!」
と言われても仕方ないような気もしてくる。
煩悩もエネルギーに変えて、煩悩を克服する。
高野山大学のK先生は「自我の解放」と言われた。確かに、そんな気もするが、、、
なかなか、それだけでは、納得できない。
しかし、仏教を学んできたものとしては、「何か深い訳がある」と思ってしまう。
(仏教への肩入れかな〜)
偉い先生方の論文や著書[3]を独学で読み、少しは調べ・考えて、後期密教を書いていくことにした。
でも、初学者が書くのは怖いな〜〜〜。
[1] 森雅秀、『マンダラの密教儀礼』、春秋社、1997
[2] シャークティ(Śakti)とは、サンスクリットで「力」「エネルギー」を意味し、特に女性神の持つ宇宙的な創造・変容の力を指す
[3] 松長有慶編『インド後期密教』(上)、(下)、春秋社、2006、田中公昭、『インド密教史』、春秋社、2022、田中公明、1997、『性と死の密教』、春秋社、1997、田中公明、『超密教 時輪タントラ』、東方出版、1994




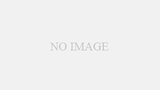
コメント