後期密教において、行者がどのような過程で悟りを開いていったのかを見てみよう。
灌頂体系
密教は文字通り、秘密の教えであり、資格を得たものにだけ示される。
その入門儀式が灌頂である。
後期密数経典『密集会タントラ』「第十八分」に基づくと、①瓶灌頂、②秘密灌頂、③般若智灌頂、④第四灌頂の4つの四灌頂を行う。そのうち、②秘密、③般若智の2つの灌頂は、性的な要素を含み、問題が多い。以下、各灌頂儀礼について、簡単に見ておこう。
1.瓶灌頂
内容は、おおむね中期密教の灌頂体系を継承するものだ。
この灌頂を受けて、「生起次第」の実習が許可される。
それ以降の3つ灌頂は、後期密教独特のものであり、究竟次第実修の資格を与えるものだ。
2. 秘密灌頂
まず受者が阿閣梨に妙齢の女性を献ずる。このとき、実際に女性が用いられる場合と、阿閣梨が瞑想に入って理想的な女性パートナーを観想するという、2つのケースがある。前者は「羯磨印」、後者は「智印」と呼ばれる。
そして阿闇梨は「印」と交わり、金剛杵(男性器)の中に蓄えられていた菩提心つまり精液を取り出し、薬指と親指の先で摘んで、弟子の口中に投入する。これによって、弟子に菩提心を授けたと観想するのである。
3.般若智灌頂
秘密灌頂を受けた弟子が女性と交わる。後期密教の本尊は、妃を抱擁する。妃は、仏の境界である「般若大楽」を象徴し、女性(妃)と交わることで、本尊の境界を悟るのである。このとき受者は、精液の放出を極力抑制しなければならない。
4.第四灌頂
前二者とは異なり「言葉のみによる灌頂の宝」であるといわれる。阿閣梨が最後に、受者に特別な教示を授けることを意味し、これを受けなければ、究竟次第を実修しても、他に講説することはできないとされている。
中期密教における灌頂儀礼は、後期密教においては、第一段階に格下げされ、土着宗教から取り入れられた性的儀礼を、第二、第三灌頂として付加したと考えられる。そしてさらに、究極的真理の伝授として第四灌頂がもちこまれたのであろう。
灌頂儀礼と言いつつ、②、③などかなり厄介な性的儀礼が持ち込まれている。ちょっと外には見せれない!当時もそんな風潮(秘密にしておく風潮)はあったようだ。
コラム:灌頂と出家者の戒律
僧侶が性的儀礼を行えば、女性との接触を禁じた戒律を犯したこととなるのは当然だ。社会的に見ても、大きな抵抗があったはず。実際、インドの後期密教を忠実に継承したチベットには、性的な儀礼を含む灌頂が紹介されたが、当然のことながら大きな問題をひき起こした。現代でもチベットでは後期密教系の四灌頂が行われているが、実際には女性パートナーを用いず、男女の精液や血液も着色された飲料などで代用されて、かなり形式化しているようで、実際の儀礼は日本密教の灌頂と大差がないといわれている。ちょっと、安心してください!
生起次第
灌頂儀礼が終われば、次は生起次第だ。
ジュニャーナパーダ流『秘密集会タントラ』では、曼荼羅の観想を十二縁起に対応づけ、受胎過程をモデルにした性理論を取り入れる。
まず白・赤・青黒の三種字(これは、白:精液、赤:経血、青:胎内に取り込まれたガンダルヴァを象徴)が口に入る無明の段階から曼荼羅が生起し、父母仏と楼閣が現れる。さらに月輪が溶解して「因の持金剛」が誕生する。これは自利円満に相当する。
次に金剛界自在母が諸尊を生む利他円満(識)へ進む。さらに、文殊金剛が出現し、感覚器官と六菩薩が配当されて六処・触・受・愛が展開する。その後、妃明処との性行為が観想され、主尊文殊金剛と妃マーマキーの誕生が「生・老死」に相当する。こうして十二縁起を曼荼羅生成に重ね、輪廻のプロセスを聖化していく。
実にわかりにくいが、要は曼荼羅の中で両性生殖により、新たな尊格が出現していく過程を観想しているのだ。このようにして、生起次第が成立する。両性生殖という部分は、中期密教と大きく異なるが、尊格の出生を曼荼羅の観想により行うという意味では、中期密教と似ている。
究竟次第
ついに究竟次第だ。人工的に神秘体験をつくりだすテクニックを基としているが、その成立について『ヘーヴァジュラ・タントラ』から、その成立過程を概観する。
『へーヴァジュラ・タントラ』
中期密教『大日経』で身体観が導入され、五字厳身観[1]により身体の要点が視覚化された。後期密教ではこれが発展し、『ヘーヴァジュラ・タントラ』で四つのチャクラと三つの脈管からなる「四輪三脈」説が確立する。
究竟次第系ヨーガでは、生殖器基底部で生じる快感を、射精を抑えて上昇させ、四つのチャクラで、四刹那と四歓喜[2]として「楽」を体験する技法が重視され、とりわけ快感を持続させる倶生歓喜の成就が究極目的とされた。精液は「世俗の菩提心」とみなされ、放出は菩提心の喪失とされるため、行者は覚醒時も睡眠時も保持に努めた。『ヘーヴァジュラ』は、身体論・快感理論・性的象徴を体系化し、生理学的ヨーガを究竟次第として確立したのである。
『サンヴァラ』系経典[3] 身体曼荼羅
『サンヴァラ』系密教では、身体そのものを曼荼羅とみなす「身体曼荼羅」が確立し、性理論を基盤とする身体論と曼荼羅観が統合された。これは行者自身の身体が宇宙の縮図=ミクロコスモスとして再解釈された。一つの後期密教の身体観の到達点であり、この思想は後に『時輪タントラ』でいっそう深化する。
後期『サンヴァラ』系の究竟次第では、特徴として「五次第」が体系化される。これについては、パクパの『チャクラサンヴァラの五次第の秘訣』[4]が、田中により詳しく解説されている。
経典ごとに、いろいろと異なる苦境次第については、そろそろ「お腹いっぱい」なので、これ以上は学者先生にお任せしよう!
おわりに
後期密教は、土着の宗教と考えられる猥雑な「尸林の宗教」から発展し、母タントラへと進んで行った。母タントラの究意次第は「楽」、つまり性快感を持続し高める生理学的ヨーガとして発展した。なぜ、このような一見反社会的とも思える宗教が発展したのか。
理由として、土着宗教が持っていたヨーガの技法が神秘的体験を得るには、かなり効果の高いものであったため、と言われる。もしかしたら、自律神経のコントロールまで可能であったのかもしれない(知らんけど!)。
土着宗教の影響:土着宗教ならかなり地域性が高く、インド全土には広がらないのでは、と思ってしまうが、、、
中世インド(8〜12世紀頃)では、仏教・ヒンドゥー両方の密教的実践者のなかに、固定寺院に属さずに全国を遊行する修行者(成就者:マハーシッダ)がいた。彼らは墓場や山中などで瞑想・儀礼を行い、地域の宗教実践や民間信仰とも接触した可能性が高いとされている。そのような行者にとっての聖地 Pīṭha(ピーティヤ)があったようだ。それにより、土着の儀礼が伝播したとされる。
もちろん、中世インドにおける農業生産力の増大や西方世界との貿易による富の蓄積により、社会に快楽的な風潮があったことも外的な要因の一つかもしれない。
土着宗教の行き過ぎた性的儀礼や墓場での儀式は、徐々に仏教教理へと高められていったようだ。
さすがに、行き過ぎた性的儀礼や墓場での儀式は、受け入れがたい人も多かっただろう。仏教教理への昇華は、当然の成り行きだったのかな〜、と思う。それでも、なかなかすごい!
性理論を受容した背景には、仏教教理が初期から輪廻転生や十二縁起の思想を持っており、性行為を死者の五蘊が新たな胎児の体内に転移する局面として、受け入れやすかったことも、性的理論を受け入れた原因かもしれない。
究竟次第のヨーガの手法を考えると、中期密教を代表する『大日経』に説かれた「五輪説」は、後期密教のチャクラ説の出発点となり、『金剛頂経』で導入された「微細瑜伽」は、後期密教で多用される生理学的ヨーガへと発展していったようだ。(発展の素地はあったのかな〜!)
ただ、直接後期密教を受け入れたチベット仏教においては、彼らの多大なる努力の結果、究竟次第をはじめとする性的儀礼が、単なる性的なカルトの域を脱し、生理学的な方法を用いた宗教実践階梯へと高められ、生き残ったと思われる。これについてはまた別の機会に述べてみたい。
チベット仏教、勉強しなくっちゃ!
[1] 五字厳身観は、『大日経』にもとづく胎蔵系の瞑想法(観法)である。修行者は、自分が、地輪・水輪・火輪・風輪・空輪を下から上に積み上げたかたちの、巨大なストゥーパに変容し、広大な宇宙空間にそびえ立っていると瞑想する。このストゥーパは、その内部に宇宙の根源的な起動因をすべて含んでおり、宇宙そのものともいえる。瞑想で実感し、修行者は自分こそが大日如来なのだという密教究極の真理を悟るのである。
[2] 四刹那とは、多様、成熟、滅息、離相を指す。『ヘーウァジュラ』で体系的に記述されており、心の状態や変化の段階を示す。四歓喜とは、歓喜、最上歓喜、離歓喜、倶生歓喜を示す。しばしば「性の快楽」という表現を用いて説明されることがあるが、肉体的な快楽にとどまらず、仏教の知恵や叡智と結びついた、より深い精神的な体験としての歓喜を指すと言われる。
[3] [田中公明、1997]では、『ヘーヴァジュラ』以後に出現した新しいサンヴァラ系タントラを、後期サンヴァラ系タントラと呼ぶ。
[4] [田中公明、1997]、p.134-142
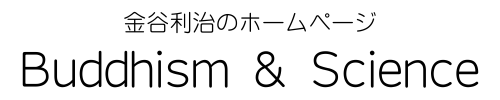



の導入-120x68.png)
コメント