ブッダが80歳で入滅した。この時、すでにインド各地には小さな僧団(サンガ)が形成されていた。布教活動は主にガンジス川流域を中心に行われ、王族や商人たちから支援を受け、仏教は結構栄えていたのだ。
ブッダは生涯で、1500~2000回ぐらいの説法を行ったようだが[1]、僧団の関心は、その「教えの正確な伝承」だった。仏陀の教えを絶やしてはいけない。だが、伝達手段は「口伝」だ。
ブッダの時代において、インドではヴェーダ文献など、すでに文字で記録する文化はあった。しかし、口伝だった。なぜかと不思議に思い、考えた。
すでに考えた人がたくさんいた[2]!それによると、時代的背景としては、書記技術や普及率が低かったことや、古代の詩や叙事詩の口伝にも価値が認められていたことがあるらしい。さらに、口伝の即時性や柔軟性に重きを置き、文字による固定化よりも生きた対話を大切にした。そのため、技術的には、韻文や反復表現・対句(対句法)など、記憶を容易にするための工夫がなされた。こうした「記憶術」が、何世代にもわたって誤りなく伝えるための仕組みとして機能したようだ。日本でも、空海が行った求聞持法などの記憶術が有名だ。
とはいえ、人間の記憶だ。地方や僧団(サンガ)により、少しずつ伝承や解釈が異なってくる。
当たり前だ!
そこで、仏教の教えを正しく伝承していくために、僧たちが集まって会議を開く。みんなで確認し合うことが重要なのだ。これを「結集(けつじゅう)」と呼ぶ。
[1]『パーリ三蔵(ティピタカ)』の経典数から推定する。パーリ仏典の「経蔵」には、ブッダとその弟子たちの説法が収められている。それらを全部集めると、ブッダの説法として記録されているものは、重複を除いてもおおよそ1500〜2000件以上あると推定されているそうだ。
[2] – Bhikkhu Bodhi Ed., The Connected Discourses of the Buddha (Wisdom Publications)/The Middle Length Discourses of the Buddha – Bhikkhu Bodhi (2005)『In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from the Pali Canon』, Wisdom Publications.
– Schopen, Gregory (1997)『Buddhist Monks and Business Matters: Still More Papers on Monastic Buddhism in India』, Routledge.
– Gombrich, Richard F. (1996)『How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings』




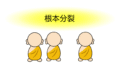
コメント