約2年半の唐滞在を経て、ついに空海は806年10月筑紫に帰ってくる。
本来は20年の留学予定だった。恵果から密教の正統をすべて授かり、たった2年半で帰国する。
日本に帰った空海の凄まじい活躍が始まる!
空海が帰国して、本当に超人的なパワーで、多くの事業を成し遂げた。それらをまとめると、以下のようになるのではないか。
空海哲学 即身成仏(そくしんじょうぶつ)などの思想の確立、後代への絶大な影響
宗教 真言密教の確立、国家儀礼化、東寺・高野山の建立
教育 綜藝種智院(しゅげいしゅちいん)の設立、知の平等の理念
書・文学 名筆家・詩文家としての文化的貢献
社会事業 治水・福祉・貧民救済など、実践仏教の展開
確かに、約2年半で密教を習得したのは驚異的だ。
でもこの短期間での帰国は結構大きな問題だ。
「恵果から言われた使命を日本で果たすことが重要と考え、早期帰国を決断した」などと言われるが、規則破りで、2年半での帰国は「闕期(けつご)の罪」[1]にあたる可能性があり、ちょっとやばかったかも。
確かに、今のように、「じゃ、明日の飛行機のチケットをとって、帰ります」とはいかない。そんな中で、なぜ、どのようにして帰国したのかは、それほど簡単な問題じゃない!
明らかになっていないようだ!
帰国後すぐには中央に召されず、しばらくは九州の大宰府(だざいふ)に滞在した。
この理由として、色々なことが言われている。みんな憶測だけれど。
- 当時、朝廷は桓武天皇の崩御、平城天皇の即位、伊予親王の変などが相次ぎ、朝廷は不安定な状況にあり、新興の僧侶の中央への登用に慎重だった説
- 2年半ほどで帰国したのは当時の規定では「闕期の罪」に当たるので処遇を考えた説
- 新しく空海が持ち帰った密教の内容や正統性を確認する必要があった説
- 空海が今後の活動準備や経典整理のため、自発的に大宰府に滞在した説
何はともあれ、数年後には朝廷に招かれ、密教の儀礼を披露する機会を得るのだ。
帰国から約6年後の812年(弘仁3年)には空海は密教の正統な継承者として評価され、嵯峨天皇により中央(朝廷)に登用され、ついに中央復帰する。
『三教指帰』を810年、嵯峨天皇に献上し、自らの学識と仏教理解を示し、朝廷の信頼を得る。単なる宗教家ではなく、「仏教に基づく国家経営」に貢献できる知識人としての自己アピールでもあったのだ。
813年以降、宮中での真言密教における重要な護摩供を実施し、国家安泰や病気平癒、雨乞いなどの祈願を行うようになる。これは、鎮護国家思想と真言密教が結びついたことを示す象徴的な出来事だ。以後、真言密教は「国家のための仏教」として、朝廷と強く連携することとなる。
嵯峨天皇との関係。嵯峨天皇は文化的教養の高い天皇として漢詩や書にも秀でていた。彼は、空海の文才や書の才能も高く評価し、個人的にも信頼していた。この親密な関係が、空海の中央での活躍にとって、「えこひいき」とは言わないが、重要なのではないか、、、
高野山と東寺 ― 真言密教の拠点建立
- 高野山
密教(真言)の修行には、深山幽谷のような静寂で神聖な地が必要であると考えていた空海は嵯峨天皇に高野山を貰い受ける上表文[2]を816年に提出し、朝廷から高野山を下賜され、山岳に新たな密教の根本道場「金剛峯寺(こんごうぶじ)」を開創した。これは、「山の密教センター」として東寺と対をなし、今でも真言宗の総本山だ。空海が高野山をどのように発見したかなどは面白いエピソードであるが、ここでは省く[3]。
- 東寺(教王護国寺(きょうおうごこくじ))
嵯峨天皇は823年に空海に対して、平安京の官寺である東寺を賜与し、真言密教の根本道場とすることを許可した。これは国家公認の寺院として、密教の弘布(ぐふ)を行う拠点が正式に認められたことを意味し、空海の宗教活動にとっては大きな転機だ。東寺は、「都市の根本道場」であり、皇室・貴族の帰依の場となったのだ。
教育機関「綜藝種智院(しゅげいしゅちいん)」の創設
空海は宗教者としてだけでなく、教育者としても偉大だ。828年、京都に「綜藝種智院」を、無償で身分を問わず学べる、当時としては画期的な学校として設立した[4]。儒教・道教・仏教の三教や、詩文・医術・天文など幅広く教授したと伝えられている。
「たとえ貧しくても学問を愛する者には、生活の援助をして学ばせるべきである。また、志をもって仏道に入ろうとする者には、その手を取り導くべきである。」
「綜藝種智院啓」には、上のような文章があり、空海の考えがよく伝わってくる。
書と文学の達人としての貢献
空海は「三筆」の一人と称され、日本書道史に名を残す名筆家でもあった。
「弘法も筆の誤り」、どこかで聞いたことがあるだろう。
有名な書には「風信帖(ふうしんちょう)」「聾瞽指帰(ろうこしいき)」「久米仙人像賛(くめせんにんぞうさん)」などがある。『文鏡秘府論(ぶんきょうひふろん)』など、漢詩文の理論書も執筆している。漢詩や散文にも優れ、『性霊集』には多数の詩文が収録されている。本当に天才だ!
社会事業と福祉活動
空海は信仰の実践として、多くの社会的活動も行なった。
讃岐の満濃池(まんのういけ)の修築(821年)、河川の治水工事(農村の灌漑支援、橋の建設など)、貧者救済、薬草栽培などの実践活動などなど[注]。もう本当に、スーパーマンだ。これだけ具体的な社会活動を行なった僧を私は知らない!
唐から、技術者集団を呼んできたのかもしれない!知らんけど!
[注] 伝承として各地に空海が治水事業、慈善事業、地域振興に参画したことが伝えられているが、これは後世の高野聖や山岳修験者によるものらしい(戸部賢、齋藤繁、日本医史学雑誌 、2022、68、pp. 221-229)
晩年と入定(入滅)
とはいえ、超人空海とて、死は避けられない。835年に高野山で入定したのだ。
ただ、これにもすごいエピソードがある。
「弘法大師[5]は今も生きて、奥の院で瞑想(禅定)している」
実際、僧侶たちが、日に2回食事を供養する。
「誰が食べるのだ!」
などと言ってはいけない。弘法大師は生きておられるのだから!

[1] 決められた留学期間を守らず帰国した罪
[2] 816年に空海が嵯峨天皇に提出したとされる「高野山請願文(高野山奏状)」と呼ばれるもので、『性霊集』巻第九に収録されている。
[3] 興味のある方は、北川真寛、『はじめての「弘法大師信仰・高野山信仰」入門』、セルバ出版、2018
[4] 821年に嵯峨上皇に対して綜藝種智院設立の趣旨を記した「綜藝種智院啓」が、『性霊集』巻第十にある。
[5] 空海の死後、醍醐天皇によって「弘法大師」の諡号を賜る(921年)



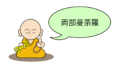
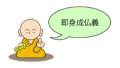
コメント