前のブログで、 “ほぼ”年代の順に空海思想・教理を示す著書と彼が行った社会事業を概観した。その思想と実践を、独断的に紐解き、空海の思想を考えてみよう。
1. 青年期の決意
空海は、結構いい家に生まれたのは以前に書いた。おかげで、15歳で平城京に上がり、18歳で大学寮に入った。しっかり教育も受けたようだ。しかし、安定した官僚への道を諦める。
まあ、大きな希望を抱いた聡明な人なら、平凡な道は選ばないだろう!
彼の決意は、24歳のとき(797年)に書いた『聾瞽指帰』[1]に見られる。すなわち、儒教・道教・仏教を比較し、道は険しくとも最高と思える仏道に進む。ただ、この書には、「衆生と共に悟る」[2]という表現があり、すでに利他の考えがあったようだ。
2. 入唐(804–806年)
804年に空海は遣唐使の一員として唐に渡った。空海は長安の青龍寺において805年冬ごろに恵果和尚に会い、806年9月ごろに唐を出発するわけであるが(恵果の入滅は807年1月とされている)、たった1年足らずで密教の全てを授かったのだ。
空海が知っていたかどうかは分からないが、密教はインドでは「師資相承」という師匠から弟子への個別伝授だ。しかし、空海が中国でみたのは制度化された「国家仏教としての密教」だった。日本に帰って空海は、国家密教を確立するが、想像を膨らますと、「個別的な師弟関係による秘儀伝授では広く民衆救済を実現できない」、むしろ「国家制度に裏づけられた密教」こそが、大規模な社会救済を可能にすると考えたのではないだろうか。
根底に利他があれば、賢い空海なら、その程度のことはすぐに思いつく!
日本で空海が展開した密教が、「国家鎮護と民衆救済」を両立させる仕組みをとして構築されたことを考えるとそのように思える。
3. 空海哲学の確立(817〜820年代前半)
帰国後、空海は『即身成仏義』『声字実相義』『吽字義』を著した。これらは、空海独自の哲学の確立を思わせる。
『即身成仏義』では、「人はこの身このままで仏」となると説く。これは、成仏は単なる個人の解脱の完成だけでなく、大日如来の智慧と慈悲を体現することだ。すなわち、仏になり「利他を行う」ことだ。別の言葉で言えば、一旦勝義諦で「空」を悟り、その後世俗諦へ降りてきて「衆生救済」をすることだ。
空海は当然「言葉は概念化を進め、言葉では真理は分からない」という大乗の教えを知っていた。それでも、『声字実相義』『吽字義』では、「真言」そのものが仏の働きであり、言葉を超えた真理を直接に表すものだと言い切り、「真実の言葉」により衆生を悟りへと導こうとした。
4. 社会的実践の展開(821〜828年)
高野山開創(816年):深山の修行道場の開設である。民衆救済とは言い難いが、自利利他両立を進めるため、僧侶の修行に必要だったのであろう。
次は利他実践の時期だ。もちろん、哲学的体系の確立と実践はオーバラップして行われたが、徐々に社会的実践にウエイトが移っていく。
満濃池修築(821年):旱魃に苦しむ讃岐の農民を救うため、巨大な灌漑池の修築を指導したのは有名だ。空海の民衆救済が具体化した最初の大事業といえる。
東寺下賜(823年);嵯峨天皇から国家鎮護の密教道場として東寺を下賜された。空海はこれを真言密教の根本道場に整備し、国家的宗教機関として発展させた。ここで彼が目指したのは、単なる個人の修行道場ではなく、国家権力の後ろ盾を得て民衆を広く救済する仕組みであった。
綜芸種智院設立(828年):貴族・僧侶に限らず庶民にも開かれた教育機関を設立した。ここでは仏教のみならず諸学問、実用的学問(算術・天文・医学など)が教授され、社会全体の知的向上を志向していたと思われる。教育による救済も、空海の利他精神の表れであった。
この時期、空海は自身の哲学を「国家制度の中で民衆に開く」という形で実現していったといえるかもしれない。
5. 理論と実践の統合
晩年の空海は、自らの思想を総合し、理論と実践を統合する著作を著している。
『十住心論』(830年頃):諸宗の教理を十段階に配列し、真言密教を最高位に置く体系を示した。
『秘蔵宝鑰』(830年頃):その要約であり、宮廷や知識層に密教の意義を分かりやすく伝えるために書かれた。
『般若心経秘鍵』(830〜835年):広く知られた般若心経に独自の密教的解釈を与え、より多くの人々がその深意に触れられるようにした。
同時期、社会事業として、東寺に施薬院や悲田院が整備され、医療や貧民救済眼された。これらの事業は、光明皇后以来の伝統を引き継ぎつつ、空海によって制度的に再編成されたものだ。彼は、単なる思想的完成にとどまらず、国家密教を通じて、教育・医療・福祉を実現し続けたのだ。
こうして晩年の著作群は、師資相承に閉じた密教ではなく、国家的制度の中で社会救済を可能にする密教を示す総決算と言えるかもしれない。
6. 空海の生涯を貫くもの
空海の生涯を貫いたものは、やはり「自利利他不二」の精神であろう。青年期の『三教指帰』においては、自己修道の決意とともに「衆生と共に」という志が芽生え、帰国後の『即身成仏義』ではそれが理論化された。『吽字義』では自利と利他が不可分であることが徹底して説かれ[3]、社会事業においては、教育・医療・福祉を通じて具体的に実践された。
この利他実践を広く社会に行き渡らせるために、インド的な師資相承ではなく、中国的な国家仏教の制度を積極的に利用したのであろう。これは彼の戦略的な一面であったような気がする。
[1] 序文と十韻詩の改訂をして朝廷に献上した際に書名を『三教指帰』に改名したとされる
[2] 「願わくは一切衆生と共に無上道を証せん」、『弘法大師空海全集』第1巻、p.26[仏道篇終結部]
[3] 「一切の如来は自利利他の二業を修して菩提を成就す。自利なければ利他なく、利他なければ自利なし。二倶に修してはじめて菩提を証す。」『吽字義』、高野山大学編『弘法大師空海全集』第2巻、p.155)



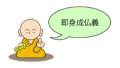

コメント