釈迦は説法を始め、80歳で入滅するまで、色々なところで、色々な人に仏教の教えを説く。
1 対機説法(たいきせっぽう)
ブッダが説法をするとき、聞く人の仏教的資質に合わせて説法をする。対機説法という。要するに、その人が分かるように教えるのだ。
有名な話に、以下のようなものがある。
息子を亡くして悲嘆に暮れていた母親は、ブッダになんとかして息子を生き返らせてくれと懇願する。するとブッダは「よろしい、これまで誰も死んだ人のいない家にいき、ケシの実をもらって来なさい。そうすれば、生き返らせてあげよう」。母親は村中を回りますが、誰も死んだ人のいない家などあるわけはない。そこで、母親は、人は死ぬことを悟るのだ。
ブッダの教え、すなわち仏教の基本的教えを述べておこう。
実は、仏教の教えは、どんどん進化している。いや、変化している。改造されている。もちろん、敬虔な仏教信者は、すべてブッダの教えだと信じている(はず)。
コラム アラカルト宗教
あるフランスの仏教学者[1]は、「ヨーロッパ人の目には、仏教は「アラカルト宗教」すなわち一人一人が各自メニューから嫌いなアイテムは避けて、好きなものだけを選ぶことができる宗教の理想的モデルのように映る」と書き始める。
要するに、仏教は多様であり、多くの矛盾する要素が含まれているが、その好きなところだけ選べばいいと言いたいのであろう。約2500年の仏教の歴史を眺めると、確かに色々な相がある。矛盾したように見えるものも多い。これは、いいように考えるべきだ。
仏教は考える宗教なのだ。絶対者が「こうだ」といったことをそのまま信じることはしないのだ。考えて、考えて、考えて、真理に近づこうとする宗教なのだ。
仏教教理の変遷、多様性などについては、後に述べるとして、まずは初期仏教おけるブッダが説いた教えについて述べよう。
2 四諦(したい)、八正道(はっしょうどう)、中道(ちゅうどう)
ブッダの最初の説法「初転法輪」では、5人の比丘に四諦(四聖諦)、八正道、中道を説いたとされる。何やら、難しそうな名前がついている。
簡単に言うと、「四諦」とは4つの真理という意味だ。「人生は苦」であるが、それを克服するにはどうするかを述べているのだ。4つの諦とは、
- 苦諦(くたい):人生には「生・老・病・死」など自分ではどうしようもない。人生は苦しみだ。
- 集諦(じったい):この苦しみは色々な欲望や、色々なものに執着するとい煩悩から生まれるのだ。これは、欲しがる気持ち(貪欲)、怒る気持ち(怒り)、真実を知らないこと(無知)(三毒(さんどく)[2])だ。
- 滅諦(めったい):この苦しみを断ち切るには、煩悩を絶たなければならない。そうすれば、悟って涅槃に行ける。
- 道諦(どうたい):悟りに至るためには、八つの正しい道(八正道)の実践だ。
悟りへ至る八つの正しい道(八正道)[3]とは、
- 正見:正しいものの見方
- 正思:正しい考え
- 正語:正しい言葉
- 正業:正しい行い
- 正命:正しい生活
- 正精進:正しい努力
- 正念:正しい気づき
- 正定:正しい瞑想
人として、まともな行いだ!特別なことではない(でも、なかなかできてないな〜)。
仏教では、生きているすべてのことが「苦」であり、人生は全て苦しみ(自分でどうしようもないこと)と考えるのだ。
ただ、やるべきことは、人間が生きていく上で大切なことで、非常にまともに思える。
さらに中道(ちゅうどう)だ!
中道とは、右や左のどちらの極端にも偏らない中間の立場ことだ。だた、もう少しい言うと、右や左の対立の考えでなく、右や左の対立を超える(右も左もないのだ、そんな区別をすることが意味ないのだ)、と言う意味のようだ。これが、後々「空」の思想に発展する!
(右と左でこの譬え話をすると、方向感覚をなくせと言っているようで、あまり良い例えではない気がするが、、、)
経典の漢字は難しい!どこの本にもこれと同じようなことが書かれているが、どうも漢字の熟語だけを見ても、意味がわからない、難しい。
日本には漢訳教典(インドの言葉(サンスクリット語)を漢文に訳したお経)が入って来ている。漢字を知っている我々は、なんとなくわかった気になる。これが曲者。実際は、我々が知っている漢字の意味と異なることも多い!
私は、多くの誤解をした。むしろ英語の方が、日常的な言葉で訳されているので、分かりやすい場合も多い!
さらに、お経は、詩の形(韻文形式、偈頌(げじゅ)[4])で書かれることが多く、意味が分かりにくい。それで多くの注釈書が書かれる。例えば、『大日経』の注釈書は『大日経疏(だいにちきょうしょ)』。さらに、注釈書の注釈書もある。おかげで、異なる解釈が出てくることも多い。経典の間で、書かれていることが異なる場合も多い。経典、なかなかの曲者である。
その後も、ブッダはいろいろなところで、いろいろな人に、説法を繰り返していく。

コラム 偶像崇拝:上の彫刻で柱上に並ぶ三つ法輪は、仏教の三宝である仏(釈尊)、法 (釈尊が発見した真理)、僧(釈尊の心理を受け継ぐ集団)を象徴している。ブッダは偶像崇拝(神や仏を具象化した像を崇拝すること)を禁じたため、法輪や仏足跡などが描かれた。しかし、1世紀ごろになるとブッダに会いたいという信仰やギリシャ文化の影響などもあり、ガンダーラなどでは、仏像が作られるようになる。
[1] ジャン=ノエル・ロベール、今枝由郎訳、『仏教の歴史―いかにして世界仏教になったか』、2023、講談社
[2] 三毒として、貪(とん)・瞋(じん)・痴(ち)という。
[3] これらは三学(戒(かい)、定(じょう)、慧(え))という大きな区分にも整理できる。戒:道徳的な生活を守ること、定:心を落ち着け集中すること、慧:真理を悟る智慧を得ること
[4] 仏典のなかで、仏の教えや仏・菩薩の徳をたたえるのに韻文(詩)の形式で述べたもの。




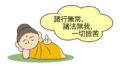
コメント