第1結集はブッダ入滅直後(紀元前5世紀ごろ)に、マハーカッサパ(摩訶迦葉)の指導のもとに、約500人の阿羅漢(あらかん、修行完成者)が集まり、行われた。場所はラージャガハ(王舎城)郊外の七葉窟だ。釈迦の教えを口伝で正確に保存するために、アーナンダが経(きょう、スッタ)を暗唱、ウパーリが律(りつ、ヴィナヤ)を唱えたらしい。この段階では、まだ集団での暗誦による伝承(口誦仏典)だ。伝統は強いのだ!
その後、教えに対する解釈やそれぞれの事情により、戒律(規則)に対する考え方が徐々に異なってくる。さあ、分裂の危機が始まる。
第2結集が、約100年後にヤサ(Yasa)の指導で、ヴェーサーリー(毘舎離)で開かれる。ここで決定的な内部対立が生じ、仏教最初の分裂「根本分裂(こんぽんぶんれつ)」が起こったのだ。
どんな意見対立が起こったか。これを見ておこう。
当時、実生活の中で厳格な戒律を守るのが難しくなり、戒律を柔軟に運用しようとする動きが出てきた。つまり戒律の緩和をめぐる議論だ。
たとえば、僧侶が托鉢(たくはつ)に行くと、食事だけでなく、時には金銭を布施される。これを受け取るのは戒律違反!それを認めるかどうかだ!また、地域によっては、「塩の保存」なども問題にされたようだ。
この問題点は「十事非法(じゅうじのひほう)」と呼ばれ、10項目の戒律緩和をめぐって、戒律を厳格に守る派(上座部(じょうざぶ)と、柔軟な解釈を主張する派(大衆部(たいしゅうぶ)が激しく対立し、分裂した。
これをきっかけに部派への分裂が始まる。
以後、約100年かけて20部派以上に細分化が進む。
一度始まった分裂は、止まらない。
そりゃ、金銭を蓄えるのは戒律違反だが、生活も安定するし、その分修行にも励める!現実派の人(大衆部)は、認めようとする。
一方、どの世界にも保守派はいる。認めない少人数(上座部)は、主に長老上座(一言でいえば、長老、偉いさん)が多かった。
今もありそうな組織内対立だ。
この分裂は、仏教の性格を大きく変える重要な転機だった。それぞれの部派は、自分たちの教えにどんどん没入していき、仏教教義を体系的・論理的に整理した論書(アビダルマ)[1]を編纂し、自分たちだけの世界に入っていったようだ!
分裂というとマイナスのイメージだ。でも、仏教の「多様性」と「教義の深化」を生むという利点(?)もあった。
とはいえ、出家者中心の思想になり、民衆からの乖離は進む!
民衆を離れた宗教だ。小乗と言われた理由の一つだろう!
[1]「仏教を理論として徹底的に掘り下げた文書(論書)」です。たとえば、「私たちは何でできているのか?」「心の働きはどう分類されるのか?」といった問いに、非常に詳細に答えようとする。


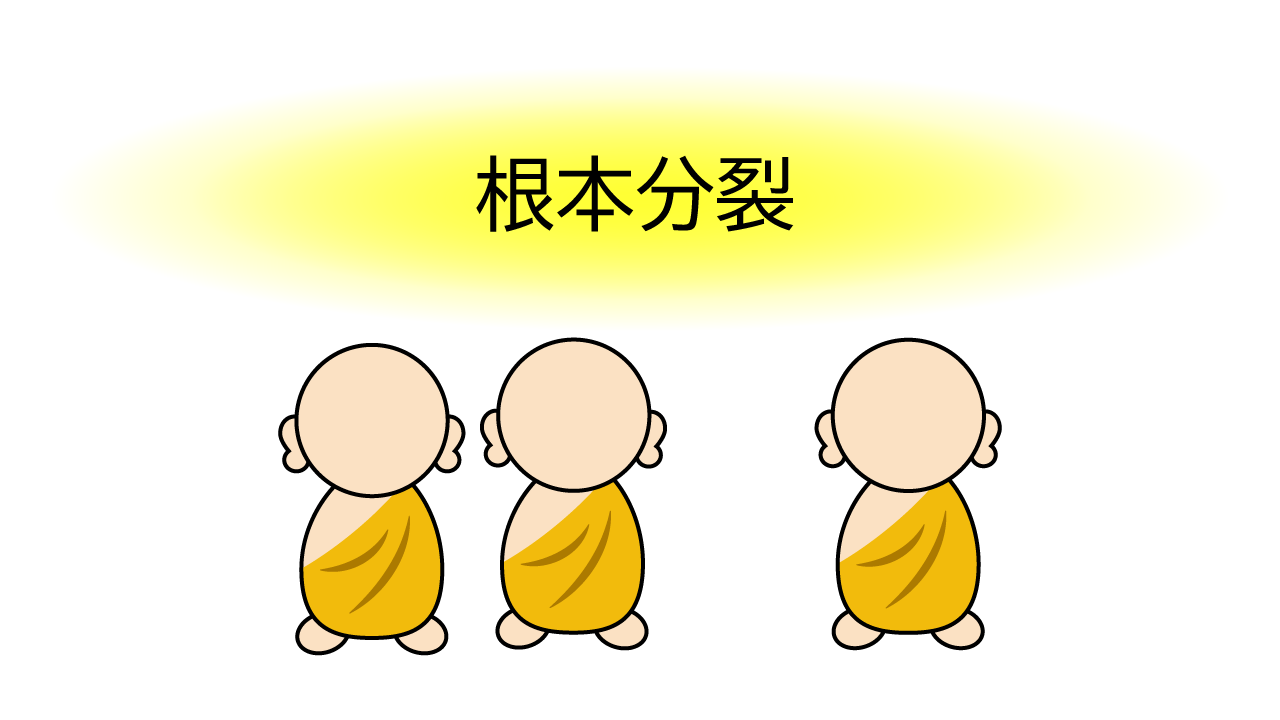

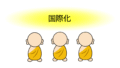
コメント