江戸時代の日本における仏教研究は、宗門での研究が中心で、宗派的な解説や注釈書にとどまる[1]。学術的な研究はほとんどない状況だった。これらのもとになったのは、江戸時代においては、当然漢訳経典だ!
明治期、政府が「国家神道」を別格に位置づけ、「廃仏毀釈」により仏教全体が社会的に抑圧され、また政治的に利用されたのはよく知られた話だ[2]。でも、鎖国も解けて西洋からの知識も入ってくる。その影響か、僧侶の間では、チベット仏教やサンスクリット仏典への関心は高まったようだ。
コメント===>当時の日本では仏典の多くが中国語訳(漢訳経典)で、その内容に矛盾が多く、原典との違いが問題視された(簡単に言うと、中国思想の影響が随所にあり、中国風にアレンジされている)。そのため、堺の河口慧海[3]は、サンスクリット経典やチベット訳に強い関心を抱くようになり、明治34年には、チベットラサのセラ寺まで行ったのだ。
大正時代から戦前の昭和期では、西洋の東洋学(特に独・仏・英)に刺激を受け、漢訳・チベット訳・サンスクリット仏典の比較研究がやっと始まったようだ。その中で、護摩を焚き、意味のわからない真言を唱える密教は「非合理・迷信・呪術的」なものと見なされたようだ。それでも、『大日経』や『金剛頂経』などの漢訳経典の校訂や註釈の再構成が進み、宗教ではなく、「学問対象としての密教」の芽が出始める。教学史・宗教史的視点からの研究も始まり、空海と最澄の対比研究も活発化したようだ。宗門の研究では、なかなか進まない領域だ。
戦後になり、「やっと」宗派的立場に偏らない、アカデミックな仏教研究者が出てきた。密教研究で言えば、高野山大学の松長有慶[4]、種智院大学の頼富本宏[5]などだ。空海が唐から持ち帰った真言密教の約1200年の歴史に比べれば、ほんと最近のことだ!仏教美術・密教図像(曼荼羅・仏頂尊)の研究が本格化し、チベット密教との比較が日本国内でも始まったのだ。
密教を歴史、思想、教理、儀礼など多角的に研究して、密教の意味を学問的また宗教的に明らかにし始めたのだ。日本密教の中心である真言密教(中期密教)の枠を超え、初期密教・後期密教・タントラ思想全体への関心が高まってきたのだ。
最近では、サンスクリット経典の復元、大正新脩大蔵経のデジタル化、図像のデータベースの構築など、新たな手法の導入、また海外研究者との連携なども強くなっているようだ。
コメント===>「宗派的立場に偏らない、アカデミックな密教研究者」が出てきたと書いた。いえ、いえ、必ずしもそうでない。仏教・密教だって宗教だ。やはり自分の宗派が正しいと思っている。上に書いた仏教学者の皆様も、その多くは宗門出身だ。後に書く密教の分類(初期、中期、後期)にもその傾向は見られる。こんなこと書くと、怒られるかな〜。
[1] ただ、江戸時代の神道を信じていた町人、富永仲基(1715-1746)が30歳のとき『出定後語』で大乗非仏説を唱えたようなものはある。「加上」説といわれ、古いものに何かを追加して新しいものが作られたとした。
[2] https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b09409/
[3] https://ja.wikipedia.org/wiki/河口慧海
[4] https://ja.wikipedia.org/wiki/松長有慶
[5] https://ja.wikipedia.org/wiki/頼富本宏


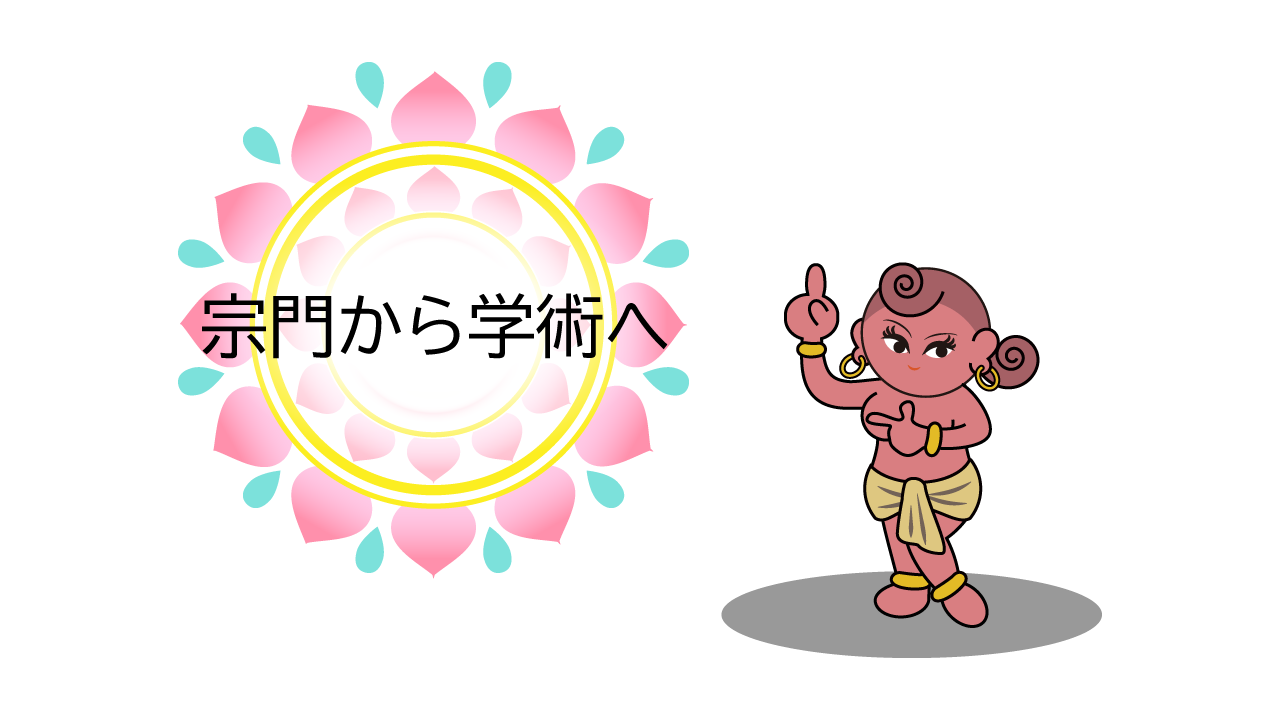


コメント