仏教の終焉:インドでの事情を少し書いておこう!インド本土では、1203年にヴィクラマシーラの大僧院がイスラム勢力の攻撃により、破壊された。インドでの仏教の終焉だ。そのため、8世紀から12世紀までインドで主流を占めた密教文献のほとんどが失われてしまい、原典に基づく研究ができなくなった。これは大変。
コメント===>ある宗教が滅ぼされると、かなり徹底的にその宗教を破壊する。日本はそんな経験を持たないようだが。
経典が残されないのは、悲しいことだが、歴史的には不思議ではないなー。
一方、仏教が伝わったチベットでは、8~11世紀にインドの成就者や学僧とチベットの翻訳家たちによって、大量の経典がチベット語に翻訳されていた。それを基にした仏教研究がなされた。とはいえ「訳語が独自で難解」「独自の註釈」「インドの儀礼や社会背景の欠落」など問題も多かった。
イギリスのインド支配:イギリスが18世紀後半から19世紀にインドを植民地にし、東インド会社を設立した。そこでは、経済支配は当然であるが、「東洋学」の整備も行なわれた。そんな事情もあり、イギリス人、ウィリアム・ジョーンズが、サンスクリット語がラテン語・ギリシア語・ゲルマン語と共通の言語(印欧語族)であるとする講演を1786年に行い、東洋に対する興味が急激に高まった。
コメント===>イギリスの大英博物館に行く。各国の素晴らしい遺跡が残されている。例えば、エジプトのミイラだ。イギリスにあるのだ!イギリスの略奪品だ!
でも、イギリスが持ち帰らなければ、現在に残されていたのだろうか?
イギリスは、インドでも仏教遺跡を発見、そして残した(アジャンタの石窟など)。
前に書いたが、サンスクリット語の発見もイギリス人だ!
日本でも同じようなことがあった。ボストン美術館に行けば分かる。
海外遺跡、海外遺産、海外美術品などの持ち出しは、善悪両方の側面を持つ。
私は、答えを持たない!みんなで議論しよう!
サンスクリット写本の発見:チベットで大量のサンスクリット写本(またはネワール文写本)が発見された!これは、19世紀末~20世紀初頭における西洋探検家・東洋学者の活動、特にイギリス・ロシア・ドイツの中央アジア探検隊の活躍だ!また、ネパールでも20世紀初頭にネワール仏教[1]の家系に伝わる写本群が発見される。その中には、『金剛頂経』をはじめとして、『秘密集会タントラ』、『ヘーヴァジュラ・タントラ』、『チャクラサンヴァラ・タントラ』など後期密教経典も含まれていた。それらを整理して、サンスクリット文献の校訂出版が出されはじめ、近代研究の基盤ができた。
19世紀後半〜20世紀初頭:ドイツ、フランス、イギリスを中心に、東洋学や比較宗教学の一環として仏教研究が発展する。その中で、ヨーロッパにおいて、仏教は「無神論的宗教」として、また「合理的で倫理的な宗教」として注目を集めたようだ。
20世紀前半:上に述べたサンスクリット写本の発見の影響もあり、文献学が重視された。原典批判、言語学的分析が研究の中心となる。サンスクリット語、パーリ語、チベット語、中国語の仏典の比較研究が進んだ。仏教をインド思想史の一部として位置づけ、ヒンドゥー教やジャイナ教との関係も検討されるようになる。
ドイツではカントやショーペンハウアーなどの思想が、仏教的なテーマ(苦、空、自己否定)との関連で注目され、仏教が、単なる宗教ではなく、「哲学的思索の対象」としても評価されるようになった。
20世紀後半:仏教を信仰や思想としてだけでなく、「瞑想」や「修行」の実践として研究する学者が出てきた。これは、研究者自身が仏教を実践してみるという新しいアプローチだ。例をあげると、「ヴィパッサナー瞑想」や「禅の修行」などを体験したうえで分析をするのだ。
同時に、「西洋が東洋を勝手に解釈してきたのでは?」という反省も出てくる。1970年代以降、「オリエンタリズム(東洋学)は西洋の都合で東洋を解釈してきたのではないか」という批判が強まる。たとえば「仏教は理性的で神がいないから素晴らしい」というのは、西洋の理性信仰に仏教を合わせて見ていたのではないかという見方だ。
コメント===>そろそろ、西洋文明の支配が変わるかもしれない!800年周期説もあるようだ[2]。ここは政治・文明問題を語る場ではないが、やっぱり、気になるな〜〜
[1] ネパールのカトマンズ盆地にすむネワール族によって信仰される密教の一派
[2] http://bunmeihousoku.com


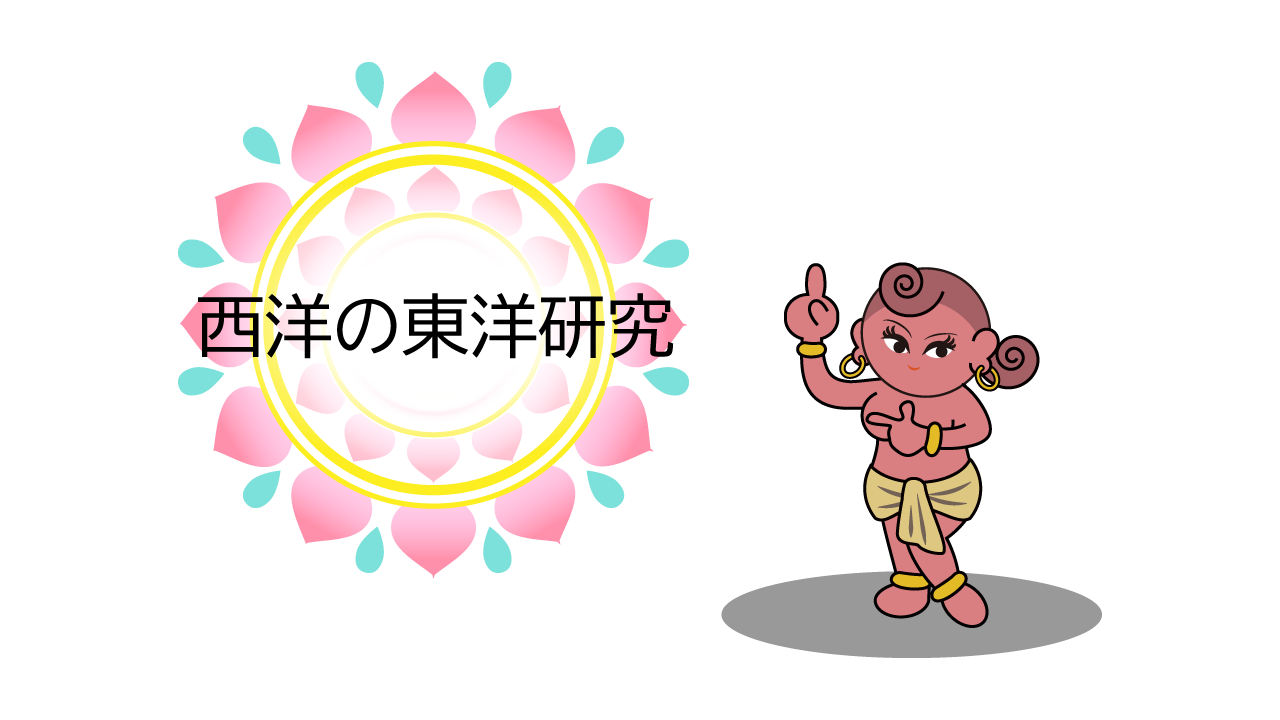

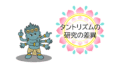
コメント