上に述べたのは、仏教全般における西洋での研究だ。密教研究に注目すれば、西洋では後期密教もしくはタントリズムの研究が非常によく進んでいるように見える。なぜだろうか〜
以下は、かなりの憶測を含むが、みなさんの意見だ!
- 欧米では、20世紀半ば以降、とくにチベット仏教に対する宗教学・人類学的関心が急増した。それはチベット動乱(1956−1959)におけるダライ・ラマの亡命(1959年)以降、チベット僧や文献が欧米に多く移動し、チベット亡命政府の支援のもと、多くの僧侶・学者が英語で教義を解説するようになっためだ。また、チベット仏教の中心が後期密教(無上瑜伽タントラ)であるため、必然的に後期密教の研究が中心となった。
- サンスクリット原典・チベット語文献の研究が大きく影響した。欧米の仏教学者は、20世紀初頭からネパール・チベットなどに残されたサンスクリット写本やチベット訳文献に基づく文献学的研究を進め、基礎文献が整備された。
(西洋の学者にとって、漢訳経典は、難物であったようだ!) - 欧米の学者の間では、無上瑜伽タントラに見られる「性儀礼」や「身体修行」に対して、フェミニズムや文化人類学的な視点からの研究が非常に盛んだ。日本の仏教学では異端とされがちなテーマも正面から取り上げる。
- 欧米では「Tantra」はヒンドゥータントラと仏教タントラの両方を含む研究対象であり、「宗教的エクスタシー」「シャーマニズム的要素」「グノーシスとの比較」など、より広範な関心から探求されている。
一方、これまでの日本の密教研究は、文献学的・教理的分析が中心となっており、欧米に比べて、対象範囲がやや限定されているように思える。もちろん、漢訳経典を自由に操れるメリットは大きく生かされているが。『大日経』のサンスクリット原典はいまだに発見されていない。それもあって、中期密教である真言密教の研究については、空海研究も含め日本の独壇場のように感じる。ただ、後期密教であるタントリズムには、性的・生理学的要素が多く、日本ではこのような側面を宗教的な視点から異端として避ける傾向が強く、研究は欧米に比べると遅れているように感じる。
コメント===>ある授業で、先生にお聞きした。
「なぜ、海外研究をあまり取り上げないのですか?」
「日本の研究が一番進んでいるからです」
とのお答えだ。
確かに、初学者が見ても、真言密教に関する研究は日本が進んでいる。
でも少し視野を広げると海外の方が進んでいる分野はある。
あまり他分野の人間が突っ込むと、大変なことになりそうなので、
「はい、そうですか。分かりました」と答えた、、、。
「まあ、確かにそれぞれの国が得意とする分野があるのは、科学でもいっしょだよなぁ〜」と思い直した。
一つの象徴的なことがある。
密教は、日本では時間軸で分類される。
- 初期密教:
- 中期密教:
- 後期密教:
中期密教は『大日経』、『金剛頂経』を中心とする空海が持ち帰った両界曼荼羅の世界である。中期密教は別名「純密」と呼ばれ、純粋な密教を意味し、初期密教は「雑密」と呼ばれ、大乗仏教と密教が混じった雑多なものを意味する。この命名からもわかるが、あくまでも真言密教が純粋で、宗教的に正しい姿としようとする意図が読み取れる。
一方、チベット、インドや西洋では、細かくはインド密教のところで書くが、内容で分類される。
日本では後期密教に属する無上瑜伽タントラは、反社会的・性的な儀礼が多く、宗教的にはもちろん、学問的にも敬遠されてきた。日本ではともかく中期密教至上主義の状況が続いてきたようだ。後期密教を避けているようにみえる。
これが、「少し視野を広げると海外の方が進んでいる分野はありそうだ」と思った原因の一つだ。
コメント===>確かに、後期密教(無上瑜伽タントラ)では、常識を超えたような儀礼が執り行われる。反社会的、性的儀礼などだ。普通に考えると日本人の感覚としては、受け入れ難い。とくに、神聖さを求める日本人の宗教的感覚からは、「え〜〜、何だこれ。堕落じゃない!」と映ってしかたない(と私も思う)。でも、インドでは8〜12世紀、とっても流行った。「なぜ?」と思ってしまう。高野山大学を卒業してから1年ほど、後期密教をかじってみた。後ほど、私的意見を述べてみよう!


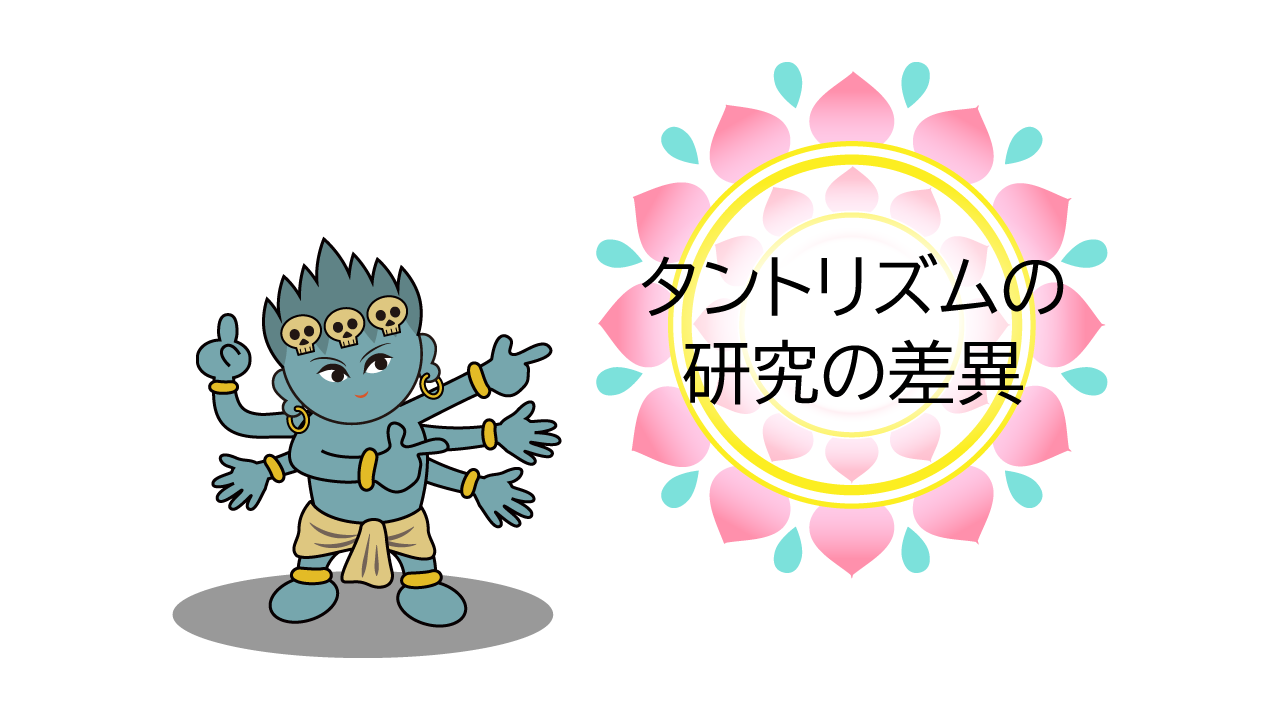

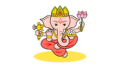
コメント