大乗仏教では、衆生の救済や悟り、そして自分の悟りを目指し、成仏することが目標だった。
ところが、インド グプタ朝[1]の頃(4世紀ぐらい)になると、現世利益的な延命、病気平癒、国家護持などの祈願がどんどん登場するようになる。同時にそれを実現するため、大乗仏教の内部にも、マントラ、陀羅尼、護法神などの呪術的・儀礼的な要素が次第に強化されていく。非常に現実的な、民衆の要求を実現するための側面が強調され始める。
コメント===>今でも、お寺に行ってお祈りするときは、合格祈願とは、病気平癒とか、家内安全とか、裕福になりますようにとか、ほとんど現世利益のお祈りだ。成仏、悟りをお祈りすることって、無いような気もする。自分だけかなぁ〜
現世利益祈の願は明らかに、仏教のヒンズー教への傾斜傾向だ。
それもそのはず、グプタ朝の諸王はほとんどが熱心なヒンズー教徒であり、ヒンズー教を国教としていた。国の保護が凄かったようだ[2]。
さらに、この時期は西域との貿易も盛んになったことや、農業生産力が向上したことなどで民衆の生活は豊かになった。人間、豊かになると現実的、享楽的な方向に向かうようだ!
ヒンズー教が強くなっても、仏教は潰されなかった
「ヒンズー教が国教になっても、仏教は潰されなかったよ」
「えー、なぜ?」
これまでの歴史を見ると、宗教が入れ替わると、古い宗教は潰される。
インドでイスラム勢力により仏教が破壊されたことを見れば明らかだ。では、なぜ?
「仏教はヒンズー教の一派だからだ」
怒る人も多いと思うが、インドでは普通の話だ。
これはインドの話で、日本の話ではない!
注釈が必要だな。
釈迦が考えた仏教では、悟りが大事で、日常儀礼や現世利益を願う儀礼は関係がなく、いわば「どうでもいい」ものなのだ。それで、日常の諸儀礼(葬式など)は旧来のヒンズー教の方式で行なっていた。そのような事情もあり、インドでは仏教はヒンズー教の一派と考えられていた。現代でもそうだ。ヒンズー教では、今もブッダはヴィシュヌ神の9番目の化身だ。潰されるわけがないのだ。
コメント===>仏教を学んでいると、しばしば思う。ヒンズー教やバラモン教、もっと言えば、インド哲学を知らないと、インド仏教は理解できない。勉強してないけど!
このように仏教のヒンズー教化は急激に進んだ。密教の始まりだ!
よく知られているが、中期密教経典として本格的な『大日経』が7世紀半ばに、『金剛頂経』が7世紀後半に成立するまでに、大乗仏教経典の密教化は徐々に進むことになる。何度も言うが、これが初期密教の時代だ。
初期密教の時代は、大乗仏教経典に徐々に密教的要素(真言、陀羅尼、護摩、曼荼羅など)が混ざり込んできて、経典としては雑多な様相を示す。言い換えれば、明確な経典分類ではなく、「ある傾向」として浮かび上がる教義的・儀礼的特徴に識別される。
このように、初期密教に関する研究は、これまで「雑密(雑部密教)」として曖昧に扱われてきたが、近年では日本・中国・西洋の学者によって再評価が進んでおり、その構造や思想、儀礼の展開について一定の理解が深まりつつあると言われる(そうだ)。
[1] グプタ朝は、古代インドにおいて、チャンドラグプタ一世により西暦320年に建国され、それから550年頃まで、パータリプトラを都として栄えた王朝である
[2] 奈良康明、「インド社会と大乗仏教」、『大乗仏教とその周辺』、講座・大乗仏教10、春秋社、pp. 35-80、1985



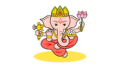

コメント