ここでは大塚伸夫による漢訳経典に基づく研究[1]を見てみよう。
大塚は、初期密教時代における漢訳経典を精読し、その変遷を密教化という観点から概観している。このような方法論の特徴の1つとして、同系列の経典に、何世紀にも渡って類本が存在する場合、その変遷を系統的に読み解けることを挙げることができる。
コメント===>結構真面目な研究紹介だ。このブログ全体の流れにそぐわない。
なぜって?
それは私が卒業論文の時に参考にした研究なので、書きたかっただけだ!
すみません!
コメント===>漢訳経典は中国の影響があるとはいえ、やはり重要な仏教資料だ。特に大塚は、長期間に渡り類本が存在する2つの経典系列に目をつける。その時間変化を追っかけて、密教化の足跡を探るのだ!
大塚は、成仏経典[2]である呉支謙訳『無量門微密持経』類本と護呪経典[3]である『孔雀経』類本[4]を取り上げる。前者は、悟りを求める経典であり大乗的である。後者は現世利益を説く経典である。
コラム:『無量門微密持経』が何故密教か
内容は非常に大乗的雰囲気にある経典であるが、どの点において、本経が密教的であることについて、大塚([2013])は以下のように述べている。
同経の最終部分では、八夜叉と八菩薩の現前守護を期待して行う儀軌が説かれる。唯一、同経の中で大乗仏教の諸思想とは異なる部分といえば、この点に限られる。すなわち、同時代に存在した大乗経典ではみな、修行者が専心する姿に諸天や鬼神が恩恵を与えるという文脈で守護が示されていた。言い換えれば、受動的である。ところが、同経の場合は八夜叉と八菩薩の現前守護を期待して行う儀軌は、修行者が守護を期待して能動的に期待して儀軌を修した結果なされるものなのである。つまり、儀軌を実践しなければ守護は得られず、儀軌の重要性が知れる。ここに、従来の初期大乗経典には見られない守護を目的とした儀軌が成立していたと見ることができる。
すなわち、密教においては、菩薩の加護(加持)を積極的に願うのである。
精読の結果、初期密教を以下の3つに区分している。
第1期:およそ3世紀前後のころより5世紀半ばころ。非仏教的なインド古来の呪術や呪文信仰に根ざしており、現世利益を目指す陀羅尼や呪文が出現し、ヒンドゥー教の影響が始まる。
第2期:5世紀半ばより6世紀ころ。陀羅尼や呪文が中心であった第1期の密教より、印契・画像・マンダラなどを扱った儀軌が出てきて、密教的レベルが上がる。
第3期:6世紀より7世紀半ばころ。悉地を得るための密教的な行法が整備される。曼荼羅や画像もより複雑化し、それらを用いた灌頂儀礼が、成仏をめざす(仏教的だ!)密教儀軌として成立する。
このように、一旦ヒンズー教の影響を受け、現世利益を求める呪術性に偏り、密教的要素(真言、陀羅尼、印契、護摩、曼荼羅など)を導入した実践体系を作り上げた。しかし、最終的には、それらの密教的要素を残しながら、目指すところは、解脱や悟りなどの非常に仏教的(大乗的)なものとなった。これを大塚は「リターン現象」と呼ぶ。
なぜ、仏教側へ戻ってくるのか?非常に興味ある問題だ。
今のところ推測だが、以下のようなことが言われている。
- 事実として、グプタ期の仏教徒の寄進銘文[5]には、「現世利益」と「成仏、解脱」の誓願の併願が多く、大乗思想が一般大衆に受け継がれて、これがリターン現象に結びついた。
- 7世紀の玄奘の『西遊記』[6]などにも記載があるが、初期密教の時代では、部派と大乗は同じ僧院で共住していた[7]。そのため、解脱を求める部派的な実践の影響があった。
- ヒンズー社会の下層に属していた初期密教修行者は、もとは解脱や成仏を目指して修行をしていたが、一旦は「ホンネ」で現世利益を求め呪術性に偏ったが、最終的には「タテマエ」ある解脱や成仏を目指し、仏教へのリターン現象へとつながった。
非常に仏教的(大乗的)なものへと戻ってきた密教はこうして、中期密教に入っていく。
急な変化ではなく、初期密教期に徐々に整備が進み、中期密教の時代に入っていくのだ。
例えば、初期密教第2期の『牟梨曼陀羅呪経』(梁代失訳)において、印契と真言の組み合わさった儀軌が初めて登場する三密行の「身」「口」の二行が出てくる。でもまだ三密行の登場とはならず、初めて明確に説かれるのは『大日経』の出現を待たねばならない。
[1] 大塚伸夫、『インド初期密教成立過程の研究』、春秋社、2013
[2] ここでは、解脱・成仏を説く経典を成仏経典と呼ぶことにする。
[3] ここでは、現世利益を求める経典を護呪経典と呼ぶことにする
[4] 大塚伸夫、「最初期密教の実態−「孔雀明王経』を中心として一」、『大正大学研究紀要』、第89号、pp. 284-308、2004
[5] 静谷正雄、『インド仏教碑銘目録』、平楽寺書店、1979
[6] 水谷真成 訳注、『大唐西域記1-3』、東洋文庫、1999
[7] ショペン・グレゴリー、小谷 信千代 訳、『大乗仏教興起時代 インドの僧院生活』、春秋社、2000




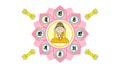
コメント