中期密教では修行者は悟りを求め、成仏を目指したが、後期密教に入ると、すでに“ヒンドゥー化”を経験した仏教が、性・死・汚れを取り込むことで、より「即効性」と「超越的パワー」を強調する方向へ行ったようだ。グル(導師)と弟子の関係が強化され、秘密裏のうちに、系統ごとに高度に儀礼化される。
後期密教では成仏の超越化、超人的能力の獲得、輪廻からの完全脱却などが求められるようになり、儀礼も中期の真言・印契・観想・護摩から、後期では性儀(男女の合一)・飲酒・死体壇修行(シャヴァサーダナ)など過激な実践へと変容していく。さらには、身体的生理学が進み、チャクラ(エネルギー中枢、もとは円、円盤の意味)・プラーナ(気、呼吸、気息)など身体技法が深化していくのだ。尊格においても、ヘールカなど怒りの尊・忿怒尊が多数登場し、男女ペア(父母仏)尊が登場するのだ!
コラム:成就者
インドで後期密教が流⾏していた時代には、数多くの在野の修⾏者たちがいて、世俗と交わりながら暮らし、悟りを求めて修⾏した。この悟りとは、涅槃や解脱よりもむしろ、空中⾶翔、遠くを⾒通せる、⼈々を操り、場合によっては呪い殺すといった、超⾃然的な能⼒の獲得を意味する。彼らは「成就したもの」すなわち「シッダ」と総称された。
彼らは、単に仏を瞑想し、その姿を⾒るだけの修⾏を低レベルのものと⾒なし、猥雑で場合によっては反社会的な修⾏法をすぐれた実践とみなしていたようだ。このような人々が、インド後期密教の時代には確かに存在した。そんな時代だったのだ!
成就者の話を集めた「八十四大成就者伝」(マハーシッダ伝)が有名だ!
参考:森政秀、「『ヘーバジュラ・タントラ』―聖と性の饗宴」、松長有慶編『インド後期密教』、(下)、春秋社、2006

中世のシッダの修行法はサドゥー(特に、ナート派)たちに受け継がれている
後期密教経典
中期密教では『大日経』、『金剛頂経』が主な経典であったが、後期密教になると父タントラ経典である『グヒヤサマージャ(秘密集会)タントラ』や母タントラ経典である『ヘーヴァジュラタントラ』、『チャクラサンヴァラタントラ』が書かれる。最終的には両者の統合とされる不二タントラ『カーラチャクラタントラ』が出てくる。
父タントラでは、『秘密集会タントラ』に続き、その理論的体系を更新するタントラが出てこなかったため、解釈学派が残った。主なものは聖者流とジュナーナパーダ流の2つだ。聖者流は主に、仏の智慧を強く打ち出し、物事の本質、つまり「すべての現象は実体を持たない(空)」という真理を深く追求する。一方、ジュナーナパーダ流では、生起次第・究竟次第の修行次第を整え、特に究竟次第では、呼吸や性的エネルギーの制御を通じて「大楽と空性の合一」を目指し、母タントラに近い方便中心の修行方法を示した。
母タントラの代表的なものには、『ヘーヴァジュラタントラ』、『チャクラサンバラ』などがある。ヘーヴァジュラなどの忿怒尊やダーキニーなど女性尊格が主尊となることが多く、仏の「慈悲」や「空性を体験する深い瞑想」を強調し、また生起次第・究竟次第を整え、性的な象徴やエネルギーを使って、「楽」の実現を目指した。
生起次第・究竟次第について、述べておこう。生起次第は、簡単に言うと、中期密教の曼荼羅観想と同じように、仏や曼荼羅を思い描き、「自分が仏と一体になる」観想のようだが、究竟次第は、なかなかのものだ!きちっとした体系化がなされるまでは、かなり神秘的、反社会的な修行も多く入っていた。後々書いていく。びっくりしないようにしてください。
多様な経典に統一性はなく、インドにおいては色々な実践・修行方法が並立しており、師資相承(グルの系統)や本尊ごとの伝統に従って展開された。つまり、実践の伝統ごとに重視する経典や儀礼が異なっていた、ということだ。たとえば、『グヒヤサマージャ(秘密集会)』と『チャクラサンヴァラ』、『ヘーヴァジュラ』などの経典は、それぞれ独立した伝統と修行体系を持つが、それらは共存しており、ある地域・時代・僧院では『グヒヤサマージャ』が重視され[1]、別の文脈では『チャクラサンヴァラ』が主尊とされていた[2]。また、同じ修行者が複数のタントラを学ぶこともあり、線引きが曖昧なことも多かった。このように、異なる実践体系が「並行的に存在」していたようだ。
でも、こんなに色々な経典・儀礼・尊格が並行して存在すると、何か統一的な解脱を求めることができるのだろうか、と思ってしまうが、インドでは、むしろ多様性が“統一的な解脱への道”として機能していたらしい。
インド思想には古くから「真理は一つ、しかしその現れや言葉は多様である」という観念があるようだ[3]。仏教においても、初期から「方便」として、衆生の能力に応じた多様な教えが許容されてきた。確かに、法華経の「方便品」にもあるな!それに、本初仏からさまざまな尊格が展開される。確かに、仏教では待機説法のように色々な方法で真理を伝えるのが普通だし、一つの仏からたくさんの化身(アバター)が出てくるな!
そう思うと、インド人の考えはすごい!
[1] – Alexis Sanderson, The Śaiva Age, 2009, in Genesis and Development of Tantrism, ed. Shingo Einoo, “Tantric Buddhism in India did not operate as a canonically unified system, but through multiple guru lineages that emphasized particular deity cults and practices.”
– Christian Wedemeyer, Making Sense of Tantric Buddhism, 2013, p. 118, “The central organizing structure in esoteric Buddhist praxis was not the taxonomic classification of texts, but rather the initiatory and instructional authority of the guru.”
[2] David Snellgrove, Indo-Tibetan Buddhism, 1987, vol.1, p.165, “Indian esoteric Buddhism was not organized into neat classifications of tantras; the reality was diverse lineages emphasizing particular deities and practices.”
[3] David Snellgrove, Indo-Tibetan Buddhism, 1987, vol.1, p.198, “In Indian Buddhism, there was always an awareness that ultimate truth is beyond conceptual grasp, and therefore multiple symbols and rituals are justified as provisional means.”
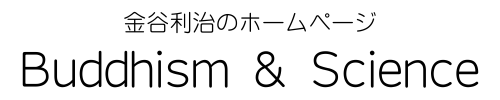


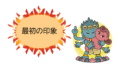
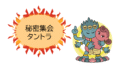
コメント