大乗仏教は、いろいろな新たな概念を生み出した。その思想的基盤を支えた2つの思想体系がある。龍樹(りゅうじゅ、インド名:ナーガルジュナ)による中観派(ちゅうがんは)と無著(むちゃく、インド名:アサンガ)・世親(せしん、インド名:ヴァスバンドゥ)による唯識派(ゆいしきは)の2つの思想体系だ。
中観派は、「空(くう)」の思想を作った。
唯識派は、「見るもの全て心の現れ」の考えを作った。
それぞれ異なる立場であるが、大乗仏教の基盤を形成したし、論争もあったが、その後の仏教哲学、実践、そして信仰の在り方にも深い影響を与えた。
4-1中観思想
龍樹(2〜3世紀)が「空(くう)」の思想を、論理的・哲学的に整理したのだ。
部派仏教アビダルマでは、精緻に心を分析した。それに対して、「すべては縁起による」「実体は存在しない」という、「空」思想を作り上げた。
よく「すべてが無(む)」と誤解されるが、実はそうではない。
「無ではない」「有でもない」「その両方でもなく、どちらでもない」と言う立場で、物事を区別しないのだ。不二(ふに)とよく言われるが、「2つではない、区別できなく、1つなのだ」のことだ。
「空」を無茶苦茶に簡単にいうと、「すべてのものはそれぞれ関係しあって成立し(縁起)、そのもの自身の本質と呼べるものはない(無自性)」ということだ。よく言われる例は、自動車。分解すると、エンジン、ハンドル、タイヤ、車体、、、、となる。
「あれ、自動車はどこにある?」
自動車という本質はなく、エンジン、ハンドル、タイヤ、車体、、、などの関係性で成り立っている。
龍樹は、言葉を否定する。我々は言葉を使うと、物事を区別してしまうため、空の世界には行き着けないので、言葉によっては真理はわからないという。龍樹の縁起説では、言葉は当然否定されるが、一旦否定された言葉が蘇るのだという[2]。空を悟った後に甦った世界を仮説(けせつ)と呼び、聖なる世界だという。縁起を3つの段階に分けることができるのだ。
1)縁起一:言葉によって表現される現象世界
2)縁起二:言葉を超えた真実(空)(聖なる世界、真理の世界)
3)縁起三:否定を受けた後、甦った言葉とそれによって示される世界(聖なるものにより聖化した世界)
これは世界には2つの真理があるという考えにとても近い。真理の二諦説(にたいせつ)という。勝義諦(しょうぎたい、究極レベル)と世俗諦(せぞくたい、現象レベル)の二重構造だ。まだ、わかりにくいな!
勝義諦とは、言葉を超え、世俗・世間の判断を超えた究極的な最高の真理のこと。世俗諦とは、世間的に認められる言葉で表現できる真理のこと。
この考えが、大乗仏教では大切だ。だって、究極的の真理(勝義諦)だけ理解しても、衆生は救えない。衆生を救うには、現実世界の真理(世俗諦)に戻らないといけないのだ。
ちょっと、言い換えると、菩薩は修行により、究極の真理(勝義諦)を悟る。しかし、衆生の救済のために現実世界の真理(世俗諦)に戻ってこなければならないのだ。
高野山大学でのある授業でD先生が教えてくれた。『般若心経』の一説に「色即是空、空即是色」とある。最初の「色即是空」は、物質(現象世界)はみんな「空」であると言う。よく分かる。次の「空即是色」は、「空」は物質(現象世界)であると言う。分からん!
先生が言うには、まずは「空」(勝義諦)を悟る、でもその後で、現象社会(世俗諦)に戻って衆生救済をする、という意味です!納得した。色々と解釈はあるようですが、衆生救済。素晴らしい!
中道も、「両極端の真ん中」と言うよりは、「空」的には「2つの相反するものに対立がないこと(不二)」だ!
コラム:龍樹の若いころのエピソード
若い龍樹についての逸話がある。彼は若い頃、非常に聡明で学識も優れていたが、世俗的な欲望、特に女性に対する欲望に溺れていた。欲望を満たすため「透明になる薬」を使い、王宮に忍び込み、性交を繰り返した。しかし、あるときその薬の効き目が切れて捕まり、処刑されそうになる。ある出家者によって助けられ、それを機に出家し、仏教修行に専念するようになった。
まあ、教訓的な作り話だと思われる。偉大な聖者であっても、出家前は強い欲望に取り憑かれていることもあるが、仏道に向かえば智慧と慈悲に変えることができるということでしょうか(今だった、こんなことしたら、1発アウトだ)。
4-2 唯識思想
無著、世親(4〜5世紀)[1]が、「意識・認識」の詳細分析による思想体系だ。簡単に言うと、「すべてが心(識)の現れ」。夢の世界のようなものだ!
もともとは、瑜伽行唯識派と呼ばれ、瑜伽(瞑想)で真理を見ようとする。そこから出てきた考えであり、瞑想で見えたものは、心(識)の現れなのだ。心だけは存在すると考えたのだ!
坐禅や観想によって、リアルに“見て・感じて・超えていく”のだ。教理を「修行の地図」として用い、それに従って実際に「観想」して悟りへと向かう。哲学と瞑想を融合した大乗仏教の実践学派と言えるかもしれない。
唯識派はものごとの捉え方(認識)には三つの段階があるとし、の三性説(さんしょうせつ)を説く。ちょっと、複雑なので、コラムに書くことにする。
コラム:三性説(面倒なら、飛ばしてね〜)
遍計所執性(へんげしょしゅうしょう)は「本当はないものを、あると思い込んでしまう心の働き。例えば、ロープを蛇と見間違えるような錯覚は有名だ。私たちは、自我・物・他人などを「実体があるもの」と錯覚しているのだ。
依他起性(えたきしょう)は、すべては因縁によって成り立っている、という仏教の基本原理(=縁起)の表現。植物の種があり、水と土と日光が揃って芽が出るように、世界のすべての現象も、原因と条件によって起こる。
円成実性(えんじょうじっしょう)は真実のあり方・悟りの境地だ。「依他起性(因縁による現象)」をありのままに見て、そこに妄想(遍計所執)を重ねない、純粋な認識のこと。「縁起を縁起として正しく理解した世界」ということだ。
これにより、「妄想の世界から悟りの世界へ至る道」を示している。
よく分からんが、、、
唯識派は、識を徹底的に追求した。視覚や聴覚などの感覚も唯識では識であると考える。感覚は5つあると考えられ、それぞれ眼識(げんしき、視覚)・耳識(にしき、聴覚)・鼻識(びしき、嗅覚)・舌識(ぜつしき、味覚)・身識(しんしき、触覚など)と呼ばれる。これは「前五識」と呼ばれる。次に意識(自覚的意識)が来る。その下に第七織である末那識(なましき)と呼ばれる潜在意識が想定される。寝てもさめても自分に執着し続ける心である。
さらにその下に第八識である阿頼耶識(あらやしき)という根本の識があり、この識が前五識・意識・末那識を生み出し、さらに身体を生み出し、他の識と相互作用して我々が「世界」であると思っているものも生み出していると考える。この無意識的深層心理阿頼耶識は、人の善悪の全ての行い(業)や経験が種子(しゅうじ)として蓄えられている心の「蔵(くら)」だ。輪廻転生においては、この阿頼耶識によって、全ての業を次の生に受け継ぐのだ。
「見るもの全て、心が描き出したもの」。時々、私もそんな感覚に襲われる。そんなことがあっても不思議ではないと思ってしまう。近い将来、映画「マトリック」の世界のようにAIが全て支配し、我々は夢を見ている。そんな世界が来ないと誰が言えるのだ!
阿頼耶識と同じような考えは、差異はあるがいろんな時代、世界中にあるようだ。神智学が言う「アカシックレコード」、ユングがいう「集合的無意識」などがそれにあたる。最近では、量子真空が作る「ゼロポイントフィールド」を人類・宇宙のすべての記憶・記録が詰まった場であると考える仮説[3]もあるようだ。別のブログで考えてみる。
コラム 阿摩羅織(あまらやしき):さらに、第九織である阿摩羅識(あまらやしき)が言われることがある。インドの唯識本典にはなく、法相宗の一部や華厳・天台系の影響を受けた唯識学者が唱えたようだ。煩悩を離れた悟りの主体であり、仏の智慧そのものとされた。「如来蔵」、「真如」、「法界」と同一とされることもあるようだ。
さらに、仏教は進化・変遷する。
一旦、現世利益の様相を示しながらも、また新たな世界を築き上げる。
ついに、密教の世界に突入する。
[1] 唯識派の世親(ヴァスバンドゥ)は、もとは「説一切有部」に属し、その教えを中心に論書『倶舎論』を著した。その後、兄の無著(アサンガ)に説得されて大乗仏教に転向し、唯識思想を確立した人物の一人だ。
[2] 立川武蔵、『初めてのインド哲学』、講談社現代新書1123、1992、pp.118-119。
[3] 田坂広志、『私は存在しない 最先端量子科学が示す新たな仮説』、光文社、2022



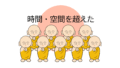

コメント