いろいろな先生がおられる。数年前までは、大学で教鞭をとっていたので、大学での授業がどのようなものかは、だいたい分かっているつもりだった。
コロナ禍の中で授業は始まったのだが、前にも書いたように事前に課題が与えられ、それをやっておくようにとの指示のある授業が多かった。コロナ禍では、それも仕方のないことだと、納得していた。
ところが、サンスクリット語初級を担当されたM先生の授業は違っていた。「参考書である辻直四郎著、『サンスクリット語文法』(岩波全書)を読んでおくように」との指示は普通だったが、
「この授業はZOOMに向かないので、対面授業になるまでやりません」
と宣言される。「いや、語学はZOOMにそれほど不向きだとは思わないがな〜」と思ったが、その時は「まあ、そんなものか」と思っていた。さて、対面授業が始まった。
文法概要を書いたプリントが配られた。「要点をまとめてくださる。いいなー」と思いきや、このプリントたくさんの手書きの訂正がある。さらに、ページが抜けている。さらに同じページが2回ある。きっと、資料準備におけるミスだろうと思い
「先生、これページ抜けています」
と指摘する。
「それ、そんなものです」
との回答。
「む〜〜???」
「そんなもの」とは如何なることか。理解不能だった。
別の機会に「先生、動詞の部分ちょっとわかりにくいので、説明してください」
「いや、そこに書いてあるので、読んでおいてください」
(無言。。。)「はい〜〜〜」
興味のあるところは、力説される。例えば、サンスクリット語が「動詞を基本とする言語」なのか「名詞を基本とする言語」なのかについては、まだ議論があるようだが、M先生は前者を強く支持され、「初級サンスクリット語の授業」において、強調される。
またあるときは、
「私は授業の予習をしたことがない」
「は〜〜〜、それで???」
授業が分かればそれで構わないが、わからないときも多い。
「先生、予習してきてください(心の声)」
もちろん、授業時間が不足していても、補講はない(と思う)。
M先生は全ての行動と発言が、「確信」と「自信」に満ち溢れている。
今どき、この手の先生はいないな〜〜。
ふと思った、私が大学生だった頃、この手の先生は結構多かった。
(ちなみに、M先生より、私の方が5歳ぐらい年上だが、、、)
「勉強は自分でやるものであり、人から教えてもらうものではない。」
最初の授業で、2、3冊の教科書か著書を教えてくれる。
「君たち、これはいい本だから、これを使いなさい」
これで1年分の講義は終わり。気が向いたら授業をする。もしくは研究室の助手(今なら、助教)が授業をする。理系では、こんな光景が当たり前のようだったな〜〜〜。
現在の高野山大学のある授業では、50年前の教室が広がっていた。



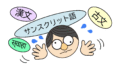
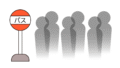
コメント